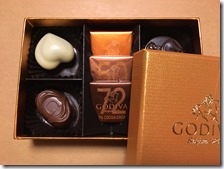来談する大学生にとって作成が難しいと言えば、「志望動機」
実際に働いた経験がないので、仕事理解も企業理解も得た情報をもとに想像していくことになります。
そしてその想像を想像で終わらせないために、更に、企業情報を確認したり、他社と比較したり、社員の方の話を聞いたりして、裏付ける企業研究を深めていくのです。
この繰り返しをどれだけ熱意をもって時間をかけたかが、志望動機の厚みに繋がります。
と、そんな説明を学生さんにしつつ、私が新卒で入社した企業への志望動機を思い出していました。
「学校という一斉指導の場以外の、個別に学べる場で教育に携わりたい」
その動機を持つに至ったのは、大学でのアルバイト経験でした。
私は当時、FAXと電話を使って、中学生に30分間の学習指導をするアルバイトをしていました。
教材販売のアフターケアのサービスでした。
その中で、ある日、中学2年生の女の子から、「勉強できないから塾でがんばろうと思ったら、塾も試験があって入れなかった」という言葉を聞きました。
塾へ行ったことのなかった私は、勉強したいと言う意欲があるのに、一定の学力がないとその意欲を受け入れてもらえない、という事実にショックを受けました。
そこで私は、学校以外で一人一人に向けた教育に関わる企業を探し、音楽教室や通信教育、個人指導塾の企業に応募していきました。
結局、その時の思いは今も続いていて、教育関係の仕事を志向する気持ちは相変わらず強いですし、屋号「Each One」も、一人一人と向き合う気持ちを仕事でも大切にしようという思いから名付けていました。
自分にとっての仕事への思い(最近よく使う「就活の軸」のような部分)は、私の場合は結局揺らがなかったなぁ…と感じています。