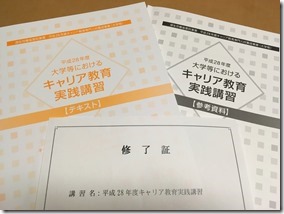女子学生でも「総合職に!」という人が増える中、まだまだ「一般職」の人気は根強いです。
特に地元志向が強い愛知近郊では、「自宅から通勤できる事務職=一般職」として希望する女子学生が多い印象。
ところが名古屋では、歴史ある女子大が金融や地元メーカー一般職の学校推薦枠を数多く持っています。
そうすると、他大学で一般職だけを目指して就職活動をしている女子学生は、それ以外の数少ない枠を希望する学生で争い、狭き門になってしまうのです。
近年、地方銀行では一般職をやめて総合職だけの募集にする銀行も増えてきていますし、採用人数が「若干名」なんていう企業もあり、より狭くなるばかり。
そこで、一般職を目指して活動している学生は企業の垣根を越え、「一般職」という枠に自由応募として選考を受けていきます。
すると、就職活動中の学生曰く、「地元企業の一般職の説明会へ行くと、同じ人ばかり」といった状況に。
「え~っ、大学推薦、無いんですか!?」
「○○大学の友達は、一般職の推薦受けるって言ってました~(T_T)」
企業説明会が始まる時期になってそう嘆く女子学生には、今からできる方法を確認しながらのサポートをすることになります。
そう考えると、本当に一般職という働き方がいいという人は、一般職に関する推薦枠の多い大学を選ぶということが選択の一つになってきます。
だったら、高校もしくは中学の段階でその選択ができるか…ということに。
早い時期から、自分の進路について考える機会も必要ですね。
その意味も含め、最近では小・中学校でもキャリア教育が盛んになってきています。
小学校や中学校の時点で、自分の将来を具体的に考える意識を持つだけでも、様々な選択の場での判断に繋がります。
ただ、人は自分や周囲の思う以上に成長します。
成長して変化したことを認めながら、成長した自分を活かせる方向へ進んでいきたいですね。