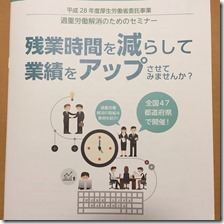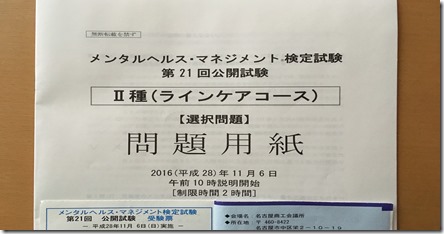世間はお休みモードでしたが、企業の採用担当者の方々はゴールデンウィーク中も休みのないところが多かったようです。
連休を挟んで就職活動は進展し、キャリアセンターを来訪する学生さん達もぐっと人数が減りました。
売り手市場ということで言えば、内々定をいただき、ひと段落した学生さんも多い様子です。
そんな中、各地の病院の看護師採用試験があちこちで行われています。
看護師は私が尊敬する仕事の一つです。
短い期間ではありますが、地元市民病院の整形外科で医療事務員として働いていた時期があり、診察室内の業務をする中で、看護師さん達がどのように働いているかも実感しています。
瞬時の判断が求められる状況や、笑ってミスをやり過ごせない内容ばかり。
そんな中、患者さんへてきぱきと処置をし、的確な説明をしている姿は、本当に尊敬できました。
看護師を目指す学生さんたちは、日々内容の濃い授業を受けていますが、さらにこの時期は、病院実習の合間を縫っての就職活動となります。
学生さんと模擬面接をする中で、よくありがちな質問である「看護師を目指した理由」や「実習で印象に残ったこと」を聞くのですが、この質問に対する回答が濃いのです。
学生さんによってもちろん回答は違うのですが、「目指した理由」によく登場する「看護師を目指すきっかけになった看護師さん」も含め、世の中の一体どれだけの看護師さんが、命や人と向き合ってがんばってくれていることか。
そんな内容を含め、看護師になりたい思いや実習での出来事を語る学生さんの回答を聞きながら、感動しうるっとしてしまうことも多いのです。
この思いを持ち続け、理想の看護師を目指し、活躍することを願っています。
そこで、まずは選考通過を。
そのために、私も精一杯力になりたいと思います。