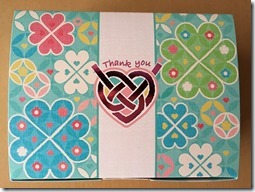春先は天候が目まぐるしく変わります。
寒かったかと思えば、汗ばむような陽気の日も。
冷たい風が吹きすさむ日もあれば、雨の日も、穏やかな日差しの日もあります。
「三寒四温」とはよく言ったものです。
そうして、着実に暖かくなっていくようです。
今日お伺いした事業所は碧南市。
思いのほか時間がかかり、往復車で3時間余りの行程となってしまいました。
穏やかな男性の方との面談でしたが、気づけば日当たりのいい応接室で、手に汗をかくほど。
日差しはすっかり春なんだと実感しました。
事業所へ向かう途中、「衣浦大橋」は渋滞していて、海の上にかかる橋の上で停まってしまいました。
私は、川を渡る橋が渋滞するのには慣れているけれど、海の上の橋は違う印象です。
ちょっと怖い感じ。
これは、私が泳げないからか…。
トラックの交通量も多く、停まっている間、橋が揺れています(^^;)
楽しい移動時間ではあるのですが、中にはそんなシーンもあり、ちょっと刺激的な半日でした。