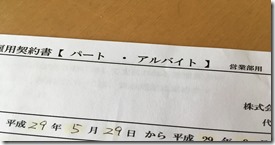今日は岐阜県瑞浪市の高校へ、就職支援ガイダンスにお伺いしました。
高校生の就職活動と言うと、大学生とは時期も流れも異なり、求人票の公開が7月1日から、選考は9月16日から、と決められています。
そして、大学生と違い、高校やハローワークとの関わりがとても強い就職活動になります。
今まさに、三者面談で希望就職先を提出し学内選考を、という時期なのでした。
私も高校へお伺いするのは初めてだったため、どんな生徒さん達が集まるのか楽しみ半分不安半分。
午前中はレクチャー中心に、そしてその時間内に作った自己PRを基に、午後から各部屋へ分かれて模擬面接を、という流れでした。
実際始まってみると、朝の不安はあっという間になくなり…。
いい意味で私の想像を裏切る生徒さん達でした。
自己PRの題材探しでは、部活や学内行事を中心に考えます。
でもそれでは題材が見つからない時は、「手伝い」も含めて考えることに。
何を書けばいいか分からない…という生徒さんも、ほんの少し言葉かけすることで、
決められた家事をどんな日でも毎日やり続ける責任感
手伝いを感謝されることに喜びを感じ生まれた他者への貢献意欲
そんな強みを働く場へ活かす、意欲にあふれた自己PRに仕上がりました。
また、社会人にとって求められるチャレンジ精神の例として、「新しい仕事を頼まれたとき引き受ける人?」と言う質問には、その部屋全員が挙手。
大学生ではなかなか全員の手が挙がらない質問なので、感動してしまいました。
私も社会人の一人として、この率直な意欲が活かされる社会であることを願い、励ましの言葉を伝えて学校を後にしました。