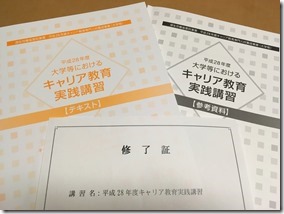私が大学生のころの「就職課」は、就職が決まったら報告へ行くところ、といった認識でした。
私が就職活動をしたのはちょうどバブルがはじける直前で、拘束という名の豪華食事接待もある時代でした。男の同級生達は、実家に泊まって地元で活動しつつ、面接の交通費を下宿から申請して稼いだり(やっちゃだめですよ)、内定数を自慢したりしていて、ほんと、氷河期の学生さん達には申し訳ない売り手市場でした。
当時は、下宿に電話帳のような分厚い就職情報誌が箱に入って送られてきました。その中に閉じこまれたハガキをせっせと書いては、資料を請求したり、セミナーに応募したりすることから、就職活動は始まりました。
男子学生の中には、背の高さほど情報誌が送りつけられていた人もいましたが、当時はまだ女子学生はお呼びでない企業も多く、私の下宿には、男子学生の3分の1にもならない量しか送られてきませんでした。
中には、私の名前を見て男と間違えて電話してきて(男女どちらもいる名前なんです)、「女の方でしたか…」と電話を切る失礼な企業(N証券)もあったくらいです。
と、いろいろありながらも、当時はほとんど自分達で活動していましたね。
ところが今は、各大学が在学生の就職活動に向けて、各種セミナーや相談できる環境を整えています。特に私立大学では、就職状況を大学を選ぶ目安にしている父兄も多く、大学志望者を増やすためにも、手厚いサポートが準備されています。
それに、2013年度の調査では、今や大学では、「キャリア教育」が授業の教育課程内で99.1%、課程外で93.0%も実施されているとのこと。
つまり、キャリアを学ぶことが単位になっているわけです。必須科目になっている大学も半数に上ります。
勤労観・職業観の育成とか、社会人基礎力を育てる授業とか、企業関係者の講演とか、内容も様々工夫されています。
早期離職を減らすため、であったり、自分らしいキャリアを考えてもらうため、であったり、私が大学生だった頃はじっくり考えてもいなかった内容について、学生と社会を繋ぐ教育として、今まさに、盛んに取り組まれています。
そんな流れの中、23日に「キャリア教育実践講習」が名古屋でも開かれており、私もキャリア教育の授業プログラム作成について学んできました。
授業プログラム集もいただけたので、より具体的なイメージが湧きました。
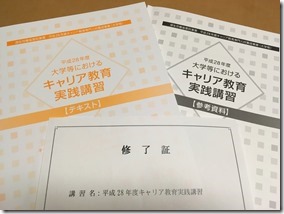
ちなみに、私が新卒で就職した法人は、内定者拘束のために内定者同士でバンドを組ませ、レッスン2回を経て内定式でライブをやるという、まぁなんとも変わったところでした。
それでも内定式当日、ギターがいないとか、キーボードがいないとか、辞退してこなかった人もいましたね。
そんな時代も懐かしい…。